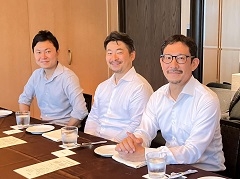Q&A
注目Q&A
| 2025/07/09 更新 | 廃油(産業廃棄物)とはどのようなものを指すのですか? |
| 2025/07/08 更新 | 木くずとは?植木の剪定枝は産業廃棄物か、一般廃棄物か |
Q&A一覧
バーゼル条約とは?概要と改正による汚れたプラスチックごみの輸出規制強化についても解説
2024/06/25 更新
 Some rights reserved by AdamCohn
Some rights reserved by AdamCohn
バーゼル条約が2021年に改正され、廃プラスチックの規制対象が拡大しました。廃プラスチック類の輸出入について定めるバーゼル条約の改正内容、また廃プラスチック類の今後についてわかりやすく解説します。
おすすめ情報
産業廃棄物のマニフェストを紛失!再交付は可能?罰則、報告義務は?正しい対処法を解説
2024/05/31 更新
 Photo by Jim Reardan on unsplash
Photo by Jim Reardan on unsplash
保存期間中のマニフェスト(A票、B2票、D票、E票)を紛失した時は、再交付ではなくコピーを保管しましょう。罰則を受けないための正しい対処法について解説します。
おすすめ情報
SDGsウォッシュとは?事例や企業にもたらす影響、リスク回避に向けた対策方法について解説
2024/05/30 更新
 Image by AbsolutVision from Unsplash
Image by AbsolutVision from Unsplash
本記事ではSDGsウォッシュの概要から事例、企業にもたらす影響、そしてSDGsウォッシュを回避する具体的な方法を解説します。
おすすめ情報